「ん゛ッ♡ふ、う゛……♡ん゛ん゛♡は、あ゛っ…………♡♡」
揺らめく炎が暗い室内をぼんやりと照らしている。少しカビっぽく、あまり清浄とは言えない空気が漂う。
それなりに広さはあるものの、窓はなく、扉は一つだけの密室。調度品の類は最低限で、生活感に乏しい。
後ろ暗い者たちがねぐらにするには、おあつらえ向きの場所だ。
「あ゛ッ♡い、い゛ゃ♡も……ッ♡あ゛ッ♡お゛ッッ♡」
そんな空間の中央で、女が一人、吊るされていた。
両手足を後ろでまとめられ、全身を這う縄がその肉体を背面へと弓なりに絞り上げている。女はその状態のまま天井から吊るされ、まるで照明器具のように揺れていた。
「また、いっちゃ、あ゛ッ♡お゛♡お゛♡〜〜〜〜〜〜〜ッッッ♡♡♡♡♡」
背はミシミシと軋むほど逆に曲がり、自重が縄をさらに食い込ませる。常人であれば数分で音を上げるほどの苦痛を受けているはずだが、女は苦悶の代わりに嬌声を響かせ、ぱっくりと開いた女性器から断続的に潮を噴き出していた。
「……何やってるんすか、あれ」
「知らねぇのか……って、お前まだ新参だったな。ありゃ野良奴隷だよ」
「いや、それはわかるっすけど……」
「頭目……カシラはああやって奴隷がイキ狂う様を見て酒を飲むのが好きなんだ」
「ええ……」
気配を殺し、扉の左右に控えていた男二人のうち若い一人が、暇を持て余して目の前の光景を尋ねる。
「あ゛♡ひ、あ゛♡お゛♡お゛♡あ♡あ゛、ぅ〜〜〜〜ッッ♡♡♡」
「……でもあれ、相当つらそうっすよ。よくあんな気持ちよさそうにしてるっすね」
「淫紋だろ。多分カシラがそういう命令してんだよ。奴隷は刻まれた淫紋に逆らえねぇからな」
「こわ~……。命令されたら、死ぬほど痛くてもイクってことっすか」
「そういうこった」
イクほどに身体を痙攣させ、身じろぎがより縄を食い込ませる。
激痛に苛まれていても、”苦痛を快感として受け取る”よう命令されれば、その肉体は忠実に従う。
ただし、行き過ぎた快感もまた地獄。どんなに泣き喚いても、奴隷である女に逃れる術はない。ただ命令者の気まぐれによって解放されるのを待つのみだ。
「おれ、野良の奴隷見るのはじめてなんで……。こんな扱い違うんすね、公共奴隷と」
「まぁ”存在しない”奴隷だからな。管理外のゴミがどうなろうと国も知ったこっちゃねぇってことだ」
ひそひそと話す男二人。自然と視線が奥へと向かう。
部屋の最奥。この空間で唯一、机や椅子といった調度品が整えられた場所。
そこでは、別の男二人が向かい合って座っていた。
「可哀想に。あれでは日が昇る頃には息絶えているでしょう」
「構わん。どうせ野良はいくらでも”作れる”」
「あ゛ッ♡お゛♡おぐ♡あ゛♡お゛ッッ♡まだいぐ、あ゛♡いっちゃ、ん゛♡♡」
身なりの良い、この場所の雰囲気には似つかわしくない男が、言葉とは裏腹に微笑みながら憐れんでみせる。
対する白髪の男はしゃがれた声で、ぞんざいに吐き捨てる。柔らかなソファに筋肉質なその身を沈め、自らが下した残酷な命令を忠実にこなす奴隷を一瞥すらしない。
彼にとって、彼女は商談室の備品であり、環境音の一つでしかなかった。
「さて、まどろっこしいのは無しだ。遠国のお貴族様が、ワシらに何の用がある」
「まどろっこしいのはお互い様ですよ。目的などとうにご承知でしょう」
女が生死を彷徨うほどイキ狂っている横で、男たちは静かに言葉を交わす。
「……そういや最近、皇国が潰れたと聞いたな」
「ええ。さすがお耳が早い」
「”どれ”だ」
「”第6”です」
短い応酬で、互いに懐を探り合う。若い男たちからカシラと呼ばれていた白髪の男は、射貫くように対面の客人を睨みつける。それはまるで獰猛な大型魔獣のそれと同じ、相手をひるませる圧倒的な威圧感を伴っていた。
だが、たった一人でここへ来た貴族は、それを飄々と受け流した。顔には柔らかな笑みを貼り付けたまま、濁った瞳が白髪の男を見定めている。
「……理由を聞きたい」
「顧客の事情は深入りしないのがお約束では?」
「今回のヤマはそれなりの数を動かす。お題目ってやつがいる」
「大所帯の組織の長もいろいろ大変ですねぇ」
「亡国とはいえ、元皇女だ。相応のリスクがある」
「理解しています。だからこそ私はここに来たのですから」
貴族の男も、椅子の背に身体を預けた。
理由を聞いた時点で、取引は成立している。だから後は、互いが互いを見定める茶番だ。
”面白いやつかどうか”。裏の世界は無法。だからこそ人としての本質がモノを言う。
「……。昔、第6皇女には煮え湯を飲まされましてね」
「私怨か。くだらねぇ」
「ええ、至極くだらない理由です。ですが、だからこそ純粋で、原始的で。……本質的な感情なのですよ。この怨嗟は」
相変わらず場に似合わぬ柔和な笑み。
しかし白髪の男は、ここにきて初めて対面に浮かぶ”歪な”表情をつぶさに観察した。
「気を悪くしないでください。”剝がれない”んですよ。笑顔が」
「……」
実際のところ、同じような依頼は多くある。復讐はもちろん、暇と金を持て余した貴族による、違法な野良奴隷の調達依頼だ。
白髪の男はそれを多額の報酬と引き換えに受けてきた。それは貴族社会との繋がりを作るためでもあり、組織をより強大にするためでもあった。だから顧客の事情など、どうでもよかった。必要なのは金と権力。それだけだ。
ただ、今回は。
この男の依頼は、少しだけ違った。
「ベギー」
「は、はいっ!」
「今回の計画、優先して進めるよう伝えろ」
「わ、わかりました!」
慌ただしく部屋を出ていく若い男を横目で見ながら、貴族の男は胸に手を当て感謝を告げた。
「今後、我が領にお越しの際は、ぜひお声掛けを」
「滅びたんだろ、おたくの国」
「今は、です。貴族も一枚岩じゃない。すぐに別の国が興ります」
「なら、ワシらにとっても悪い話じゃないな」
「そういうことです」
混乱は新たな秩序を生む。そして秩序を作る側に立った者がその利益を享受する。
それは幾度時代が移り変わっても変わらない、この世界の摂理だ。
「さて。フォグト」
「はい」
「この客人を送ってくる。アレの片付けは任せた」
「承知しました」
「欲しかったら持って帰ってもいい」
「え? いや、カシラのお気に入りじゃなかったんですか?」
男たちが一瞥した先には、度重なる強制絶頂により息も絶え絶えとなった女の姿。
もはや絶頂による反応も薄れ、声も掠れ。力なくぶら下がったそれは、屠殺前の家畜に見えた。
「かひゅ……♡はひ……ッ♡」
「声が良いから鑑賞用に置いていただけだ。喉が潰れた肉に興味は無い」
「なら、まぁ、遠慮なく」
新たな秩序がどれだけ不条理で、理不尽で、倫理に反していようと。
一度動き出せば、それはやがて”常識”となる。
その常識はこいつら奴隷をさらに憐れな存在へと貶めるだろう、と部下の男は憐れんだ。
「腕を出せ。所有権を渡す」
「はい」
「”法の神の名のもとに”」
白髪の男の腕から発せられた光が、部下の男の腕へ吸い込まれていく。
たったこれだけで、女の所有権は書き換えられた。
この光景を見るたびに、部下の男は身震いする。
何せ、奴隷制度は”法の神の名のもとに”認められているのだ。
人知を超えた存在が後ろ盾となっている以上、奴隷が救われることなどあり得ない。
「何度考えてもおっかねぇ……」
せめて自分が奴隷に堕ちてしまわないよう気を付けなければ。
頭目と客人が去った部屋の中で。部下の男は一人気を引き締めながら、女を吊るす縄に手を伸ばした。
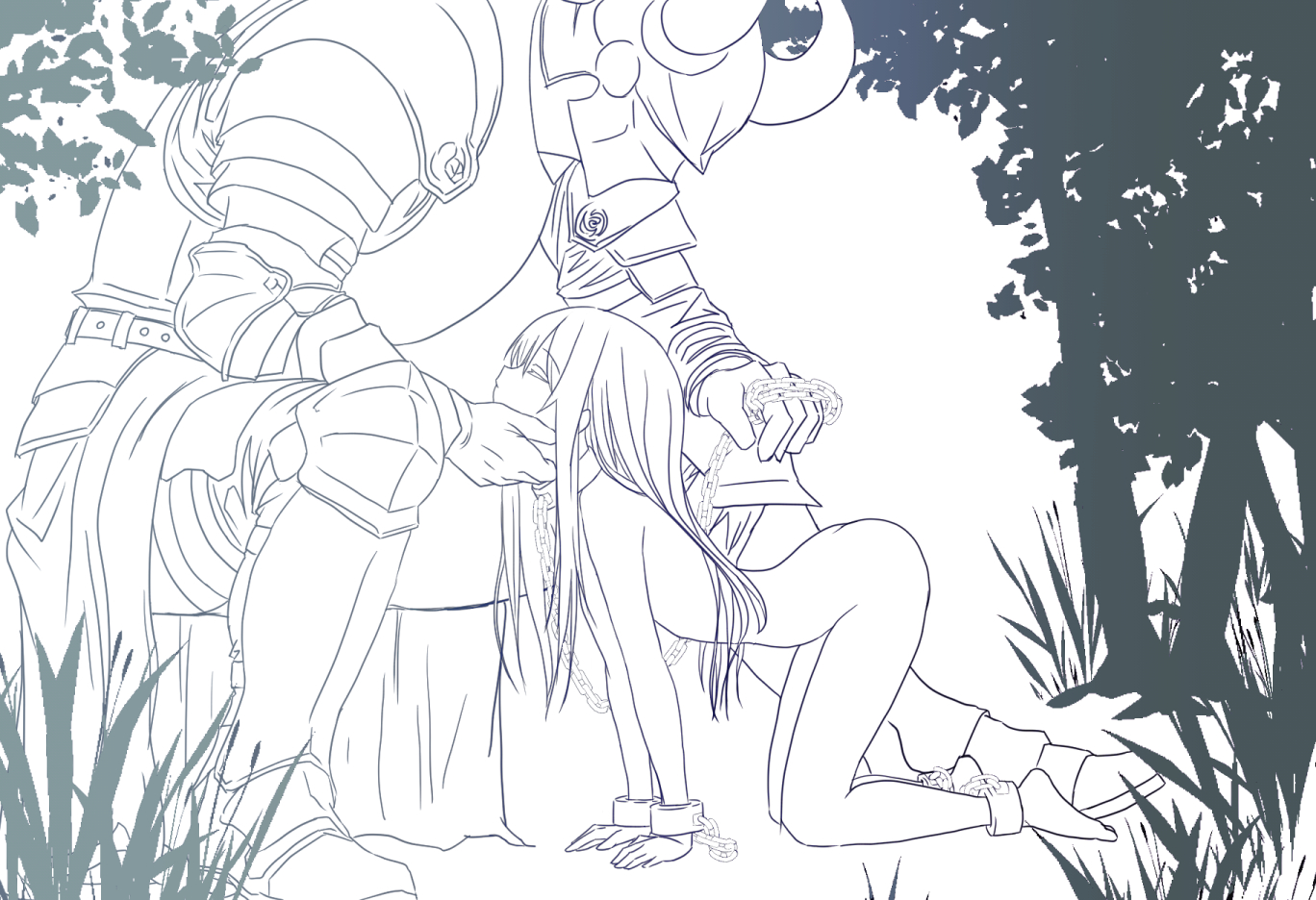 短編
短編

コメント